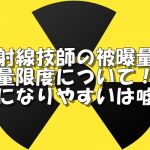病院では様々な検査があり放射線技師が関わるものとしてはレントゲン、CT、MRI、超音波、X線透視など誰しもがなんとなく思い浮かべることのできる検査が並びますが、核医学・RI検査と聞いてもあまりピンとこないのではないでしょうか?
他の検査に比べて受けたことがある人も少ないですし、核というだけで恐怖心を持ってしまう人もいるようですので、今回は謎に包まれた核医学・RI検査について紹介をしていきます!
僕がRIについてマスターというか理解したのは技師として現場で働き始めてからで、国家試験を受けた時点でもサッパリ意味が分かりませんでした。
座学の勉強では200問中20問も出題されるので必死に頭に詰めて無理やり覚えていましたが。。。
目次
RI検査とは?検査方法や画像作成の原理などまとめ!
ラジオアイソトープを使う検査です
RI検査のRIって何?という話ですけど、ラジオアイソトープ(Radioisotope:放射性同位体)を略したもので、ラジオアイソトープとは放射線を放出する元素のことをいいます。
福島原発事故が原因で空気中に撒き散らされてしまった放射性物質であるセシウム137やヨウ素131も放射性同位体すなわちRIですね。
ここまでをシンプルにまとめると放射線を出す物質のことをRI(放射性同位体)ということです。カンタンですね。
RI検査を日本語で言うと核医学検査となります。
放射線同位体検査と言うのが正解なんでしょうけど、ややこしいし長いので核医学と大雑把にまとめる風潮ができて定着したようです!?
RIが入った薬を体内に入れる
次にRIことラジオアイソトープをどのようにして検査に使うかということですが、放射性医薬品といってRIが入った薬を患者さんの体内に静脈注射、経口投与、口や鼻から吸入させるのです!
これだけ聞くと何とも恐ろしいですが放射線の量は極々少なくて、健康に影響を与えることは無いので安心して下さい。
薬が投与されてから数時間~数日は体内から体外へと常に放射線が出ている人間になりますけど、体内に投与された本人にすら悪影響は発生しないので外出を制限されたり人と接することを禁じられたりすることはありません。
ただRIを使った治療目的(バセドウ病や甲状腺癌の治療にヨウ素131が使われます)となると話は別で、3日間ほど専用の治療病室に収容されてしまいます(T_T)

こちらは主に心臓の検査に使われる塩化タリウム201が含まれた放射性薬品で、放射線が外部に漏れない様に左の大きな白いパッケージの中に、右の小さなバイアル瓶が格納されています。
極微量とはいっても無駄な被曝をさせないのが原則なので厳重に梱包されていますし、注射するときのシリンジ(注射器)にはタングステンや鉛で作られた放射線を遮蔽する用のカバーを装着します。
これは放射性医薬品を取り扱う医師、看護師、薬剤師、そして放射線技師を守るための措置ですね。

黒っぽいのがシリンジシールドといって放射線を遮蔽してくれるのです!欠点としては重くなるということ!
体内の臓器や骨に集積する
体内に投与された放射性医薬品はどうなるのかというと、それぞれ薬の性質によって体内の臓器や骨に移動していきます。
以下は薬と集まるところと病院で使われる検査名です。
- 201TLCl:心臓(心筋)に集まる→心筋シンチグラフィ
- 99mTc-MDP:骨に集まる→骨シンチグラフィ
- 99mTc-MAG3:腎臓(尿路系)に集まる→腎シンチグラフィ
- 67Ga-クエン酸:腫瘍や炎症を起こしている箇所に集まる→腫瘍、炎症シンチフラフィ
- 99mTc-MAA:肺に集まる:肺血流シンチグラフィ
- Na123I:甲状腺に集まる:甲状腺シンチグラフィ
SPCETで体内から出る放射線のデータをもとに画像化する
放射性医薬品を投与したのなら後は画像化するだけですが、どのように画像化するかというとSPECT(スペクト)という装置に患者さんを寝かして体内から出てくる放射線を検出するのです。
動画が今までをまとめてくれたような内容となっていて、パッと見でCTやMRIのように見えるのがSPCET(Single photon emission computed tomography:単一光子放射断層撮影)という医療機器。
SPECTは上下2面の検出器を体に近づけることで体内から出てくる放射線を検出する装置なので、SPECT自体はMRIと同じく放射線を出す能力は持っていません。
SPCETの画像
例として99mTc-MDPという骨に集まる性質を持つ放射性薬品を使う骨シンチグラフィという検査をするとこのような画像ができます。
骨に集積するということで画像化すると当然、骨の絵が浮かび上がります!画像が左右2つありますが読影しやすくするためにコントラストと明るさを変えた物で同一の被検者です。

骨盤恥骨上の膀胱部分が黒く写っているのは99mTc-MDPは尿として排出されるからで膀胱に溜まっていることを表しています。
骨シンチグラフィは99mTc-MDPを投与してから約3時間後(骨に集まる時間を待つため)に撮影をはじめますが、検査前には必ずトイレに行かせておしっこをしてもらいます!その理由としては膀胱に溜まった99mTc-MDPを排出させて余計な情報を除外するためです。
何が分かるの?
先程の画像は健康な人の画像なので骨が見えただけですが、実際に病気を持っている人を撮影するとこのような画像になります。

被検者は肝細胞癌を持っており転移を調べるために骨シンチグラフィ検査をしたところ、右腸骨にホットスポット(高集積部)があり転移が判明しました。
他に腫瘍転移の他に、分かりやすいものでいえば骨折箇所も分かりますね。
左上腕骨が骨折したとしたら当然その箇所がホットスポットとなるので意味を理解すると単純で分かりやすく面白い検査です。
SPCETとPETがRI検査
癌検診で注目を集めているPETもアイソトープを使用するのでRI検査の内の1つとなります。
最近はSPCET装置、PET装置をCT、MRIと組み合わせたSPCET-CTやPET-MRIといったハイブリッド型も登場していて益々、RI検査というのが分かりにくくなっていますが。。。検査の方法や画像化する原理みたいなのは何となく分かって頂けたのかなと思います。
ドクターからRI、核医学検査を受けましょうと言われても恐れることはないということだけ知っておいていただけたら幸いです。