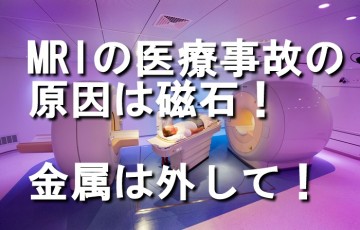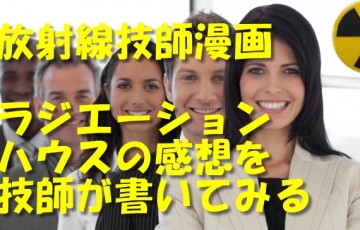撮影音は大きい・検査時間は長い・撮影前にやたらと体をチェックされるなどなど謎が多いMRIという機械、見た目はCTと似てますが全く別物です。
この記事ではMRIで体内画像が撮影できる原理について小学生でも分かるように解説をしていきます!
放射線技師会の少し自虐的な特設ホームページである「みんなに知ってもらいたい診療放射線技師のこと」 では、MRIについてこんな風に解説されています。
人の体の70%を占める水に含まれる水素原子が、強い磁場に反応する性質を 利用して、人体のあらゆる方角の断面を撮影する検査です。X線と比べて骨や 空気の影響を受けにくく、脳や柔らかい組織の検査に適しています。
分かるような分からないようなですね。。。
体内の70%は水:エイチツーオー(H2O)だから、水素原子Hを利用して画像化しているよ!っていうことを言っていますが、さらにカンタンに言うと要は体の水分を利用しています。
ただこの後の強い磁場に反応する性質ってのが、意味不明ですね。
投げやり感が半端なく伝わってきますが、この部分をイメージしやすいように解説してみます。
目次
MRIの撮影原理とは?を凄く簡単に紹介
そもそもMRIって何の略?
MRIとはMagnetic Resonance Imagingの頭文字をとった略称で、日本語で言うと「核磁気共鳴画像法」
英語でも日本語でも意味が分かりませんね(x_x;)
ここで知っておいて欲しいのが最初の単語であるMagnetic!
日本語に直訳すると「磁石の・磁気の~」って意味になります。
要は磁石を使った撮影装置だよ!ということを、まずは理解して頂ければと思います。
撮影原理は磁石の力
小学生の理科でお馴染みの砂鉄をイメージすると分かりやすいと思います。
理科の実験で紙の上に砂鉄を巻いて、裏からマグネットを当てると下の画像のようになりますよね?これが磁場です!
マグネットの磁場に沿って砂鉄が規則正しく整列をしていますが、MRIもこの原理を利用しています。
あとは人間の体こと人体に当てはめて考えるだけ!
マグネット=MRIの装置、砂鉄=体内の水分
凄いアバウトですがマグネット=MRIの装置、砂鉄=体内の水分として考えてみて下さい。
マグネットの磁石、磁場の力(MRI)を利用して、体内の細胞や組織に存在する水分を規則正しく整列させることで、コンピューターが読み取り画像化することができるのです!
MRIの撮影時間が長いのは、水分を整列させるのに時間が掛かるのが原因です。
30分ぐらいかかっても怒らずに動かないでいて下さい。
せっかく整列しそうだった水:H2OのHがバラバラになって、今までの時間が台無しになってしまいますので。。。見つかるはずだった病気も見つけることができなくなってしまいます。
そして磁場のかけ方によって整列の仕方も変わるのでCTと違って色々な撮影法があり、撮影中に音が「ギーギーギー」・「キィーキィーキィー」とか変わる理由ですね。
さらに骨を白く写したり、黒く写したりっていうことが可能。
もちろん水分もね! この様々な撮影法を駆使して対象疾患に適した検査プログラムを実施します。
水分を利用するから椎間板が写る
ヘルニアで有名な椎間板は、よくスポンジにたとえられますね。
レントゲンではスカスカすぎてX線が透過してしまい画像になりませんが、MRIは水分を利用しているので椎間板でも画像化することができます!
血管を造影剤を使わずして3D化できるのは水分の微妙な差でもコントラストを付けることができるからです。
あと放射線を使わないのでもちろん被曝はしませんので、産婦人科領域では超音波と並んでメジャーな検査方法です。
フーリエ変換もしてるよ
頭でイメージしやすいように説明できたとは思いますが、、、実際はもっと複雑ですね。
画像化するにはフーリエ変換がどうたらこうたらとか
数学好きな人は調べてみると面白いかもしれません!
今回の僕の説明はあくまで技師会の説明に補足を勝手にしてみたということでお許しを(x_x;)