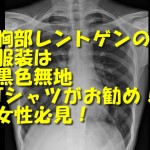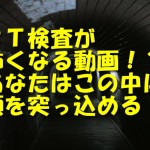診療放射線技師になったら、まず最初に覚える撮影でなおかつ働き続ける限りお付き合いをしていかなければらない胸部レントゲンの撮影方法、条件やポジショニングにおける注意点を教科書に載ってることだけではなく、自らの経験を交えながら書いてみます。
レントゲンを撮る機会が無い人にも見ていただけるように息を吸って止める理由や、腕を外側に向けられる理由なども紹介していきます!
目次
撮影条件
- 管電圧:120~140kVの高圧撮影
- 管電流:200mA
- 撮影時間:0.05s以下(心臓の拍動の影響を最小限にするため)
- 撮影距離:200cm
- グリッド:10:1~12:1の高グリッドの物を使用
高電圧撮影は透過力が増して、写真のコントラストは低下しますが、肋骨影・石灰化が淡くなり、肺野陰影が見やすく、心臓・横隔膜に重なる部分の肺野も描出できます。
撮影時間は0.05s以下を厳守!長くなると心拍動により画像にボヤケ、ブレが出ます。
最近は自動露出機構(AEC)、フォトタイマを使って設定濃度になったら、自動的に曝射を終えるタイプが増えてきています。
撮影距離は拡大率を抑えるために、200cmと他の撮影より長くとりますがCTR(心胸郭比)の評価に影響をあたえるためです。
ポジショニング
- 照射野・フィルムの中心にPA方向で真っ直ぐ立ってもらい、肩を力を抜いて下げます
- 肩甲骨の陰影が肺野から除外するために、掌を外側に向けて(両手背を腰に付ける)肘を前に出します
PAで撮る理由(背側から撮影)
心陰影の拡大防止です。APだとCTRが10%程、過大評価になります
衣服について
男性は基本的に上半身裸です。
女性にはブラジャーを外すように説明をして検査着に着替えて貰います。
外す理由を説明するときはワイヤーや背中のホック(金具)部分が写るからと言って下さい。
病院・医療機関によって無地のTシャツならOK!などルールは違いますので郷に従って下さい。
ネックレスはもちろん、湿布・エレキバン等も撮影範囲に含まれていたら外してもらいます。
入射点・中心線
第6~7胸椎の高さ(肩甲骨の下縁が目安)で、フィルムに対して垂直、正中面に入射します。
フィルムサイズ・照射野
上は肺尖部から、下は肋膜角まで欠かさないように肺野全体を撮ります。
フィルムのサイズは女性は大角、男性は半切ってザックリ言われることもありますが、性別ではなく患者さんの体型から判断しましょう!
先輩にどうやってフィルムサイズ決めてる?って聞かれたときに性別で分けてますって答えたら多分怒られます。
- 痩せ形の人=胸郭が狭いので、肺野は縦に長くなります。
- 肥満型の人=胸郭が広いので、肺野は前後方向に広がることができ、縦は短いです。
次に照射野ですが、上限を第7頸椎(隆椎)に合わせれば、肺尖部が欠けることは無いから安心だよって教えられたりしますが、基本的に照射野は中心に来る入射点を基にして考えましょう。
撮影の実施
息を吸ってー止めて下さい!と合図をしたらバクシャスイッチを押して撮影です!
スイッチを押すときは必ず患者さんの状態を確認しましょう。
息止め不良、体動の可能性があります。
観察対象
肺動静脈、気道、気管支、大血管、横隔膜、心臓、肺尖域、胸郭など
動画
実際のポジショニングの動画です。
この動画で1つ抜けている点がありましたが分かりましたか?
答えは肩甲骨を外す気が全くないということ!
前の手すりを持たせているだけです(x_x;)
高齢者の方だとふら付いて転倒の恐れがあるので持たせますが基本は外して撮影します。
胸部写真の確認点
次は撮影した写真を見ての確認点です。

こちらの写真を例として解説していきます。
左右の肺野濃度は均一か
左と右とで濃度に違いが見られた場合は疾患を疑うのではなくて、まず自分の撮影にミスが無かったかを考えましょう。
入射点のズレ、X線管球の角度、身体の傾きなどによって左右差が出ることがあります。
グリッドを使うので、少しのミスで濃度差の原因となります。
左右の濃度が違うのに、肺野血管影に著名な所見を認めない場合は、ほとんどの場合、撮影側に原因があります。
左右差が出てしまった。。。ダイナミックレンジ圧縮処理で誤魔化そう!って考えは絶対にやめてください。
見る人が見たら簡単にバレます。
素直に上司に報告をして再撮影するなり、画像処理するなりの対応をしてください。
肩甲骨陰影が外せているか
例の写真で見ると左側は、肺野領域に重なるようにして肩甲骨陰影が写っていますね。
右側も十分外せてるとは言い難いです。
手を抜くと、このように証拠として残りますので、毎回しっかりと肩甲骨は外すように心がけましょう。
骨陰影、横隔膜と重なる部分
骨陰影(主に肋骨)、横隔膜と重なる部分の血管影を、目で追えない場合は、撮影条件、グリッド、画像処理のパラメータ等を再度見直しましょう。
1枚のレントゲン写真で肺野血管影はもちろんのこと縦隔部、気管支、横隔膜、骨陰影をうまくバランスをとって写しだすことが大切です。
体動によるボケは無いか
画像にボケ、ブレが見られた場合は撮影の瞬間に患者さんが動いてしまった可能性があります。
本当に曝射のスイッチを押したタイミングで、運悪く患者さんが動いたのなら仕方ないですけど大抵は、患者さんの様子を見ずに撮影したからボケタ(x_x;)っていうのが多いです。
どんな撮影であっても、曝射するときは必ず患者さんの様子を確認しましょう。
吸気で撮れているか
ボケと同じで、患者さんが息止めをしているかは、必ず確認が必要。
適当に撮ると、過去写真と比べられてバレますので。
当たり前のことを言いますがレントゲン写真というのは嘘を付かず真実のみを映し出します。
肺野が欠けていないか
肺尖から横隔膜後ろの肺野まで、十分描出されているか確認。
観察対象をギリギリに撮ってこそカッコイイ!みたいな考え方をしてる技師が極稀にいますけどね。。。
照射野に関しては、ほとんどの施設で半切or大角サイズから絞ったりすることはないと思います。
胸部写真のフィルムサイズの見極めは2択だからこそ重要!肺野が短い人を半切で撮ってしまったときの格好悪い写真は恥ずかしいですよ。
胸部撮影のまとめ
あらゆる撮影の基礎が詰め込まれている胸部写真!
数ある撮影の中でも覚えることや、気を付けるべきことが多い方に位置しています。
だからこそ、正しい知識を身に付けることは大事です。
初めて撮影、ポジショニングについて書いた記事なので、なんともまとまりのない感じになってしまいましたが。。。
少しでも参考にしていただけたら幸いです。